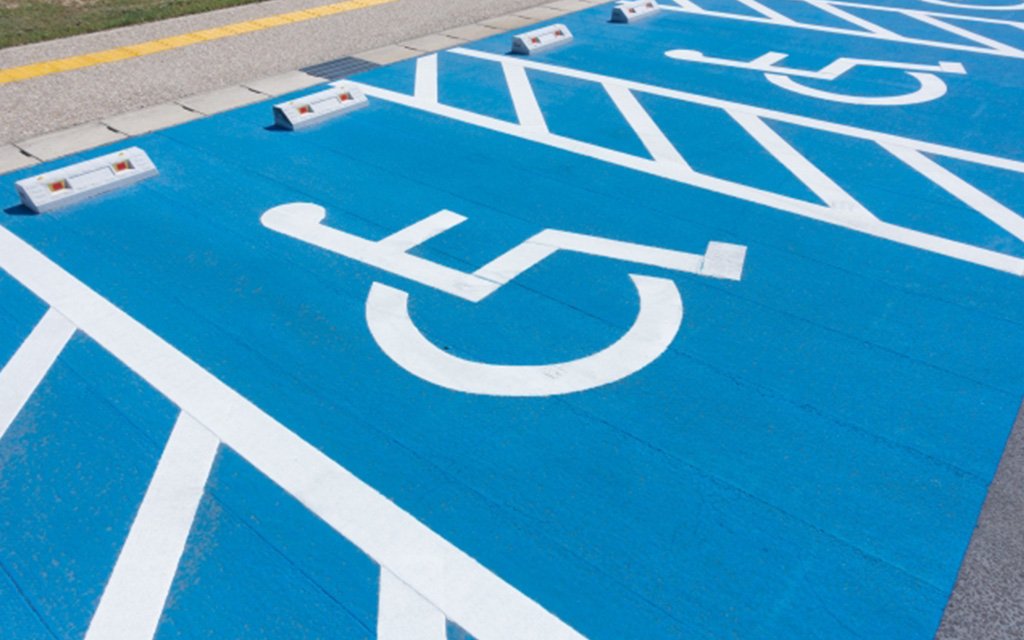商業施設やサービスエリアなどの駐車場で、車椅子マークのついた駐車スペースを見かけることがあります。「車椅子を使用している方が利用する駐車場かな?」となんとなく理解はしていても、利用方法などがわからない方も多いかもしれません。
近年、この駐車スペースを必要な人が利用しやすいように「パーキング・パーミット制度」というものを導入している自治体が増えています。そこで、本記事ではこの制度の内容や利用方法などをわかりやすく解説します。
- 目次
-
1.パーキング・パーミット制度とは?
車椅子マークのついた駐車スペースのことを正式には「障害者等用駐車区画」と呼びます。これは、障がいのある方や高齢者、妊産婦、けがをした方など、歩行が困難な人が利用できる駐車スペースです。
パーキング・パーミット制度とは、「障害者等用駐車区画の利用対象者を限定し、対象者に利用証を交付する」という制度です。地方自治体ごとに導入されていて、パーキング・パーミット制度の他に、「思いやり駐車場制度」「ゆずりあい駐車場制度」など、自治体によって名称が異なります。
パーキング・パーミット制度が導入された背景
障害者等用駐車区画は、「本来必要な人以外が駐車していて、対象者が利用できない」「駐車区画が不足している」などの理由で、設置の目的通りに利用できていないという実態があります。そこで、適正な利用を推進するために、利用可能な対象者を明確にするパーキング・パーミット制度が導入されました。
制度を導入している自治体は?
パーキング・パーミット制度は、2006年に佐賀県で導入されたのが始まりで、2021年末現在、40府県4市で導入が進んでいます。国土交通省の調べによると、パーキング・パーミット制度を導入した自治体の約9割が、障害者等用駐車区画の適正利用が進んだと回答しています。
2.障害者等用駐車区画とは?
それでは、障害者等用駐車区画とは、具体的にどういったものなのでしょうか?これは「バリアフリー法」で公共施設や商業施設などに設置が求められている、車椅子使用者等のための駐車スペースのことです。障害者等用駐車区画には、次の特徴があります。
- 建物の出入口やエレベーターホールなどに近い
- 車椅子で乗り降りできるように一般の駐車区画よりも幅が広い(横幅3.5m以上)
- 車椅子のマークの掲示や青などの色分けがされている
車椅子のマークは、正式には「障害者のための国際シンボルマーク」と呼ばれています。世界共通のシンボルマークで、車椅子に限らず障がい者が利用できる建物・施設であることを示しています。
また、障害者等用駐車区画の他に、建物の入口付近に設置された横幅25mほどの一般幅の駐車区画をパーキング・パーミット制度の対象としている自治体もあります。これは、高齢者や妊産婦の方など歩行は困難でも車椅子は使用せず、幅が広い区画を必要としない人向けのものです。
3.制度の対象者は?
パーキング・パーミット制度の対象になる方は、歩行が困難と認められる方です。具体的には、おもに以下のような方です。自治体によって対象となる障がいや等級は異なりますので、お住まいの市区町村役場などに確認してください。
- 身体に障がいのある方
- 知的障がいをお持ちの方
- 要介護の高齢者
- 難病を患っている方
- 妊産婦の方
- 歩行が困難なけがをした方
心臓、腎臓、呼吸器機能の障がいなどで歩行が困難な方も対象になります。このため、外見からはわかりづらい方も利用証があることで、障害者等用駐車区画を利用しやすくなるというメリットがあります。
4.利用証ってどんなもの?
パーキング・パーミット制度の利用証は、自治体によってデザインや内容が異なります。主な種類と使い方を見てみましょう。
利用証の種類

大きく分けると、車椅子を使用するか使用しないかで分けている自治体、有効期限で分けている自治体などがあります。
たとえば、佐賀県の場合は、身体に障がいのある方や高齢者など、長期間歩行が困難な方向けに、5年間の有効期限で緑色の利用証を発行しています。また、妊産婦やけがをした方など、一定の期間だけ歩行が困難な方には、有効期限が原則1年未満のオレンジ色の利用証を発行しています。
利用証の使い方
車いすマークなどが記された駐車場に停めたら、利用証をルームミラーにかけるなどして、おもて面が車外から見えるように掲示します。ダッシュボードや座席などに置くと外から見えづらいため、注意が必要です。
また、居住地域で発行された利用証があれば、パーキング・パーミット制度を導入している他の自治体でも利用ができるため、旅先などでも使うことができます。ただし、自治体によって利用条件が異なることがありますので、事前に確認しておくと安心でしょう。
5.利用証の申請方法は?
自治体が定めた要件を満たしていれば、申請することで利用証を受け取ることができます。ここでは、申請に必要なおもな書類や申請方法を解説します。自治体によって異なりますので、必ず居住地域の自治体に確認しましょう。
必要な書類
交付申請書
確認書類
- 身体に障がいのある方:身体障害者手帳の写し
- 高齢者:介護保険被保険者証の写し
- 難病を患っている方:特定医療費(指定難病)受給者証の写し
- 知的障がいの方:療育手帳の写し
- 妊産婦の方:身分証明書、母子健康手帳
- けがや病気の方:身分証明書、歩行困難であることと加療期間が明記されている診断書の写し
申請場所、申請方法
申請方法は、自治体や各保健福祉事務所などの窓口での申請、または郵送での申請になります。インターネットでの電子申請を受け付けている自治体もあります。
窓口での申請の場合、必要な書類や要件が満たされていれば、即日交付が可能です。申請手数料は無料です。郵送の場合は、必要書類とあわせて、140円分の返信用切手を同封します。
6.監修コメント
パーキング・パーミット制度の話になると、よく持ち上がるのが不適正利用についてです。車椅子マークの表示に加え、塗装などで区画を目立たせることで、不適正利用を防ぐ効果が期待できるとの意見もあります。そのための取り組みとして、区画の塗装に必要な用品を貸し出している自治体もあります。
罰則などを設ければ、障害者等用駐車区画の不適正利用を防止できるかもしれません。ただそうすると、ぎすぎすした社会になりかねません。すべての人が気持ちよく駐車場を利用できるように、マナーを守り、パーキング・パーミット制度の周知に努めていきたいものです。